こんにちは、スポーツ愛好者の皆さん!
今日は、投球に関する運動療法についてお話ししたいと思います。
特に、投球動作がうまくいかないときにどのようなアプローチが有効か、そしてその中で手首や足の使い方がどれほど重要かを解説します。
運動療法の基本的な進め方
まず最初に、筋肉の力が不足している場合、どのようにしてその力を回復させるかを考えます。
特に、手の筋肉(中手筋群や球筋群)のテストで問題があった場合、運動療法を段階的に進める必要があります。
初めに、治療者が手を動かすサポートをし、次第に患者自身で動かす練習を進めていきます。
最初は補助的な運動から始め、少しずつ自分でできる範囲を広げていきます。
最終的には、抵抗をかけて筋肉を鍛え、協調的な動きを取り戻すことが目標です。
このような段階的な負荷をかける方法が、筋力の回復を助けます。
持久力の改善法
また、持久力に問題がある場合もあります。
例えば、野球のピッチャーであれば、投球数を目標に合わせて運動を繰り返します。
最初は少ない回数からスタートし、少しずつセット数を増やしていくことが重要です。
例えば、最初は「10回10セット、計100回」を目指し、少しずつその回数を増やしていきます。
持久力を鍛えることで、投球時に疲れにくくなり、パフォーマンスの向上が期待できます。
投球動作の改善:手首と指の使い方
投球動作の中で、手首や指をうまく使えないと、投球の方向が定まらず、肘や肩に無駄な負担がかかってしまいます。
これを防ぐためには、手首を適切な角度で動かし、指や手のひらの使い方を改善することが必要です。
特に、浅指屈筋(指を曲げる筋肉)が強く働きすぎていると、投球のリリースが早くなり、腕や肘の負担が増える原因になります。
最初は軽くボールを握り、指の内側でしっかりと保持する練習を行い、手内在筋を使ってボールを安定させることから始めます。
その後、立った状態でボールを真上に投げる練習を繰り返し、最終的にはバックスピンをかけてボールを上に押し出すような動作に繋げます。
このように、指や手首の動きを意識することで、ボールのリリースポイントを正しく前方に持ってくることができます。
投球動作における肘と肩の使い方
投球の最後で重要なのは、ボールをリリースするタイミングです。
特に、肘が投球方向に向きすぎてしまうと、肘や肩に不自然なストレスがかかります。
そのため、肘を投球方向に向けすぎず、肩関節と体幹をうまく使って投げることが重要です。
投球動作は、下肢(足の動き)から始まって上に伝わる運動連鎖で行われます。
足をしっかり踏み込んで、体幹と股関節を回旋させることで、腕に必要な力を伝えることができます。
これを意識して練習することで、肘の突き出しや肩の負担を減らすことができます。
足の動きが影響する
投球動作において、足の筋力や使い方も重要な要素です。
特に、足の指をうまく使わないと、全体の運動連鎖がうまくいきません。
固いスパイクを履いて運動をしている場合、足の指で踏ん張るのではなく、足首を底屈させて無理に踏み込む癖がついてしまうことがあります。
このような場合、足の指を強化し、足に適切に重心をかける練習を行うことが必要です。
足の筋力を改善することで、投球動作全体の精度やパフォーマンスが向上します。
まとめ:手の機能と運動連鎖の重要性
投球障害を防ぐためには、下肢から始まる運動連鎖に加えて、手の機能も重要です。
手内在筋と手外在筋を協力させた動作を再構築することで、よりスムーズで効率的な投球動作が実現できます。
スポーツ現場で簡単にできる手内在筋テストを活用することで、早期に問題を発見し、機能不全を改善することが可能です。
手の小さな筋肉の機能を意識して鍛えることで、投球時のパフォーマンス向上と怪我の予防が期待できます。
最後に、手の筋力が弱い場合、それが元々の問題なのか、それとも投球動作を繰り返すうちに悪化したのかについては、まだ確定的な結論は出ていません。
今後、さらに研究を進める必要がある分野です。
運動療法を実践することで、投球動作の改善や怪我の予防が期待できるので、ぜひ取り入れてみてくださいね!
【参考文献】
栗田 健,手内在筋と投球障害 ボールリリース時の手の機能から内側型野球肘障害を考える:理学療法ジャーナル 第55巻 第6号, 2021年6月15日発行.
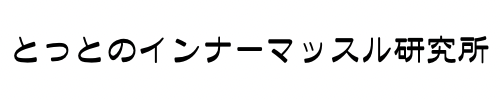



コメント