こんにちは!前編では、プロ野球のピッチャーがどれだけ肩に負担をかけて投げているか、そしてその負担を支えている「回旋筋腱板(かいせんきんけんばん)」について紹介しました。
後編では、どうやってその筋肉を守り、鍛えるのか?
リハビリやトレーニングの工夫をわかりやすく解説していきます!
まずは“状態チェック”から始めよう!
ケガをした選手にいきなりトレーニングさせるのではなく、まずは「状態のチェック」から。
特に問題になりやすいのは、肩の後ろ側にある筋肉(棘下筋や小円筋)。
これらが固くなっていたり、筋肉同士がスムーズに動かなくなっていたりすると、うまく投げられません。
そこで、病院などでは「超音波」を使って、筋肉の動きや柔らかさをチェック。
問題があれば、まず手でゆるめたりほぐしたりしてから、トレーニングに入るようにしています。
回旋筋腱板のトレーニングの3つのポイント!
肩の小さな筋肉をうまく鍛えるために、大切なポイントが3つあります。
①強度(どれくらいの負荷で鍛えるか)
- 最初はごく軽い負荷(10%くらいの力)で始めます。
→ 小さい筋肉にピンポイントで効かせるため。 - 少しずつ負荷を上げて、投球に近い強さ(70~100%の力)に慣らしていくことが大事。
②収縮の種類(どうやって筋肉を動かすか)
- 最初は力を入れても動かさない「等尺性収縮」からスタート。
→ 例えば「押してるけど動かない」みたいな動き。 - 次に動かしながら縮める「求心性収縮」、
→ 肘を曲げながら引きつけるような動き。 - そして引っぱられながら力を入れる「遠心性収縮」へ。
→ 腕を伸ばされながらも耐えるような動き。 - 最後には「プライオメトリクス」という瞬発力を高めるトレーニングを加えて、実戦に近づけていきます。
③運動のスタイル(姿勢や動かし方)
- トレーニングには大きく分けて2種類あります。
① 閉鎖性運動連鎖(CKC)
→ 手を固定した状態で体を動かす(例:腕立て伏せ)
→ 肩に安定した負荷がかかりやすい!
② 開放性運動連鎖(OKC)
→ 腕だけを自由に動かす(例:ダンベルを持って上げ下げ) - 特にCKC(閉鎖性)のほうが、三角筋の負担を減らして回旋筋腱板に効きやすいと言われています。
投げ始める前に「腕立て伏せテスト」!
キャッチボールやピッチングを始める前に、ある“テスト”を行います。
それが…
- 両手で腕立ての姿勢をキープできるか?
- 片手で腕立ての姿勢をキープできるか?
これで、肩にしっかり力が入るか、筋肉が反応するかを見ているんです。
ちゃんとできていれば、いよいよ投球再開!
まとめ:地味だけど超大事なトレーニング
「回旋筋腱板トレーニング」は、派手ではありません。
でも、ピッチャーの命ともいえる肩を守るには、欠かせない土台です。
実際にプロの現場では、
- 超音波で動きのチェック
- 軽い負荷から始める
- 投球に近い姿勢で筋肉を鍛える
といった、段階的で工夫されたトレーニングが行われています。
野球をする人、ピッチャーの子どもを持つ保護者、運動指導に関わる人にとっても、
「肩を守るには、こんな地道な努力があるんだな」と知ってもらえたら嬉しいです!
【参考文献】
岡田匡史, 野球における回旋筋腱板トレーニング:理学療法ジャーナル 第55巻 第6号, 2021年6月15日発行.
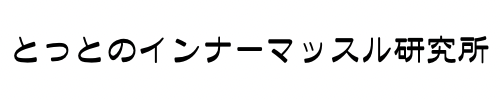


コメント